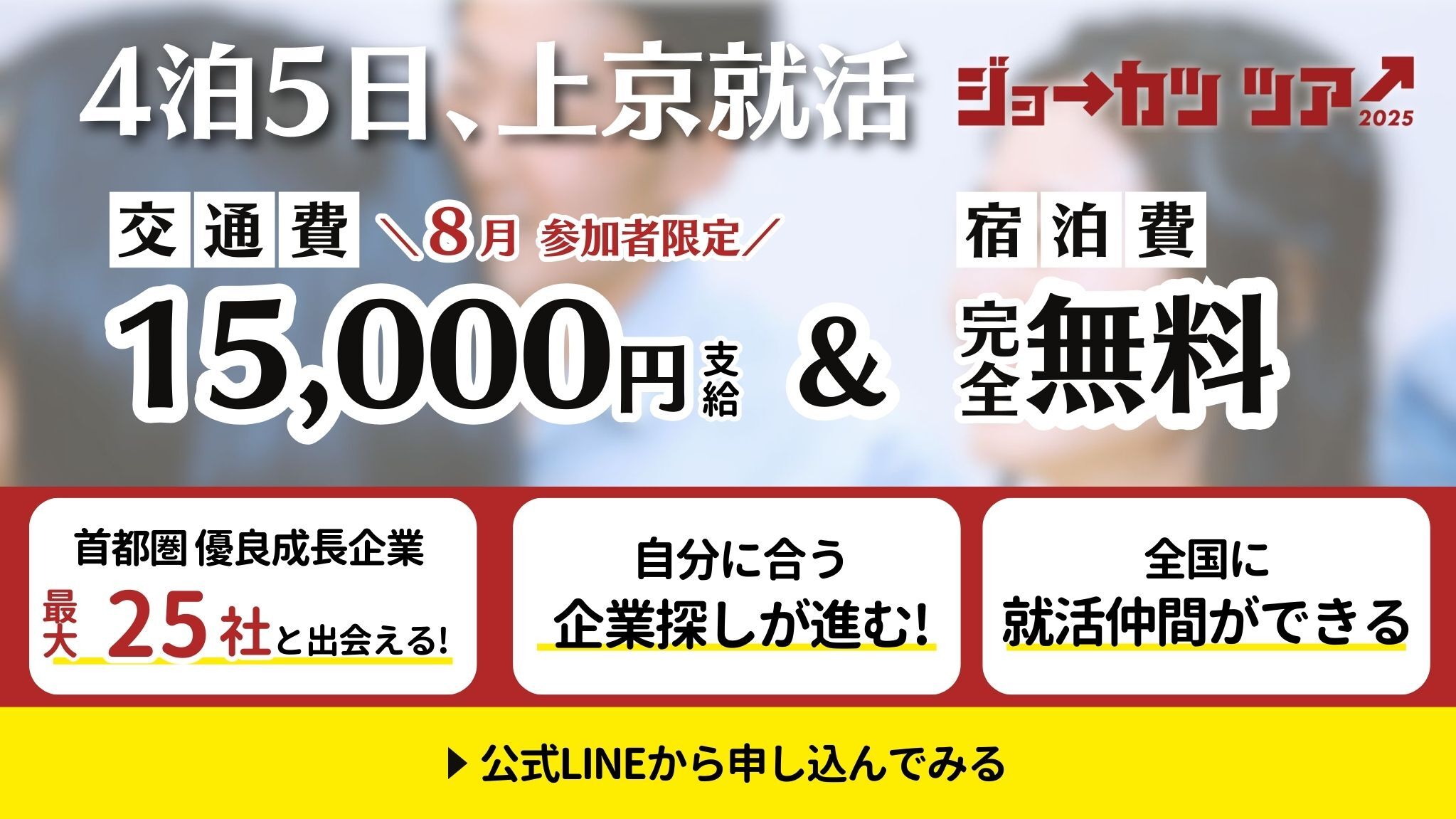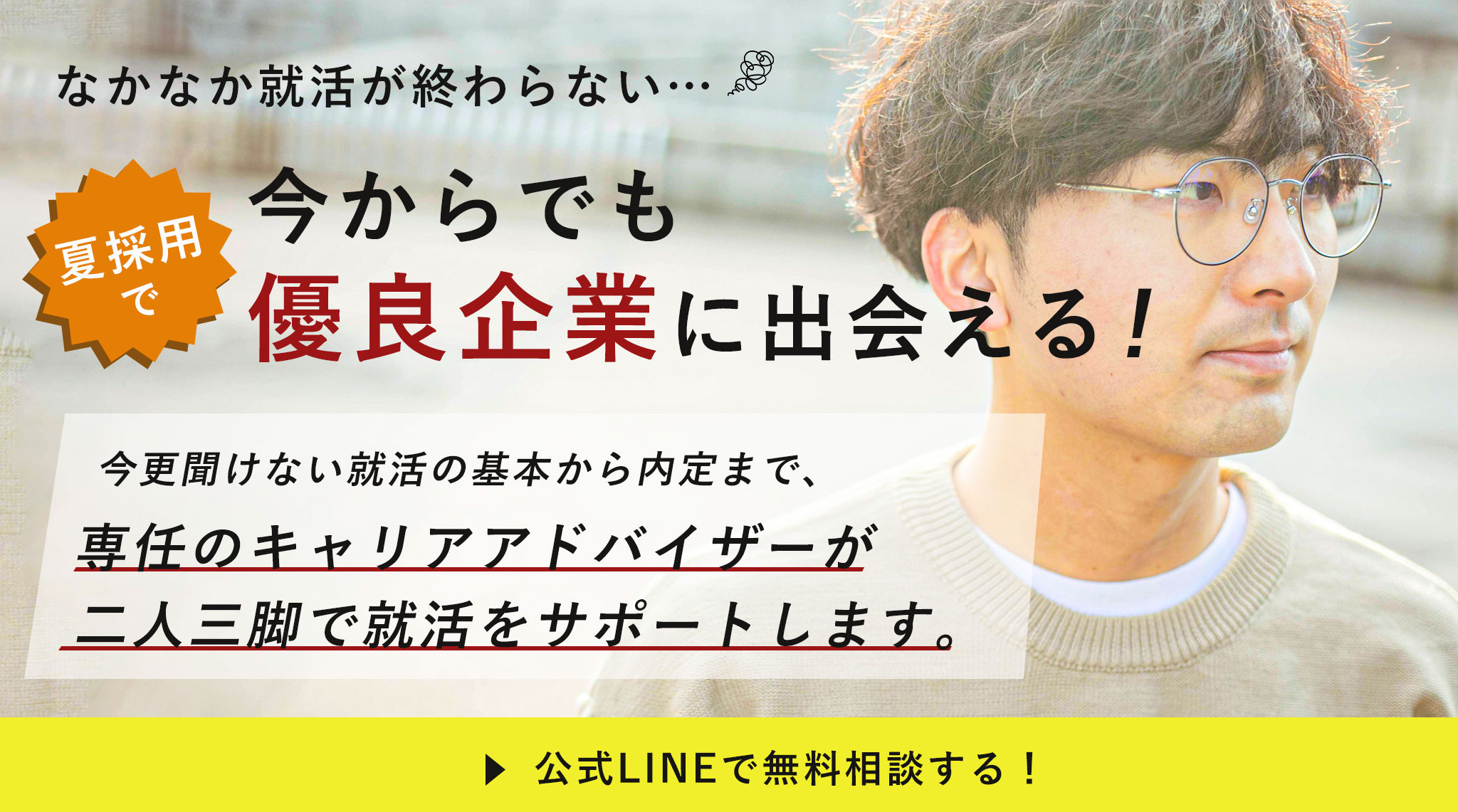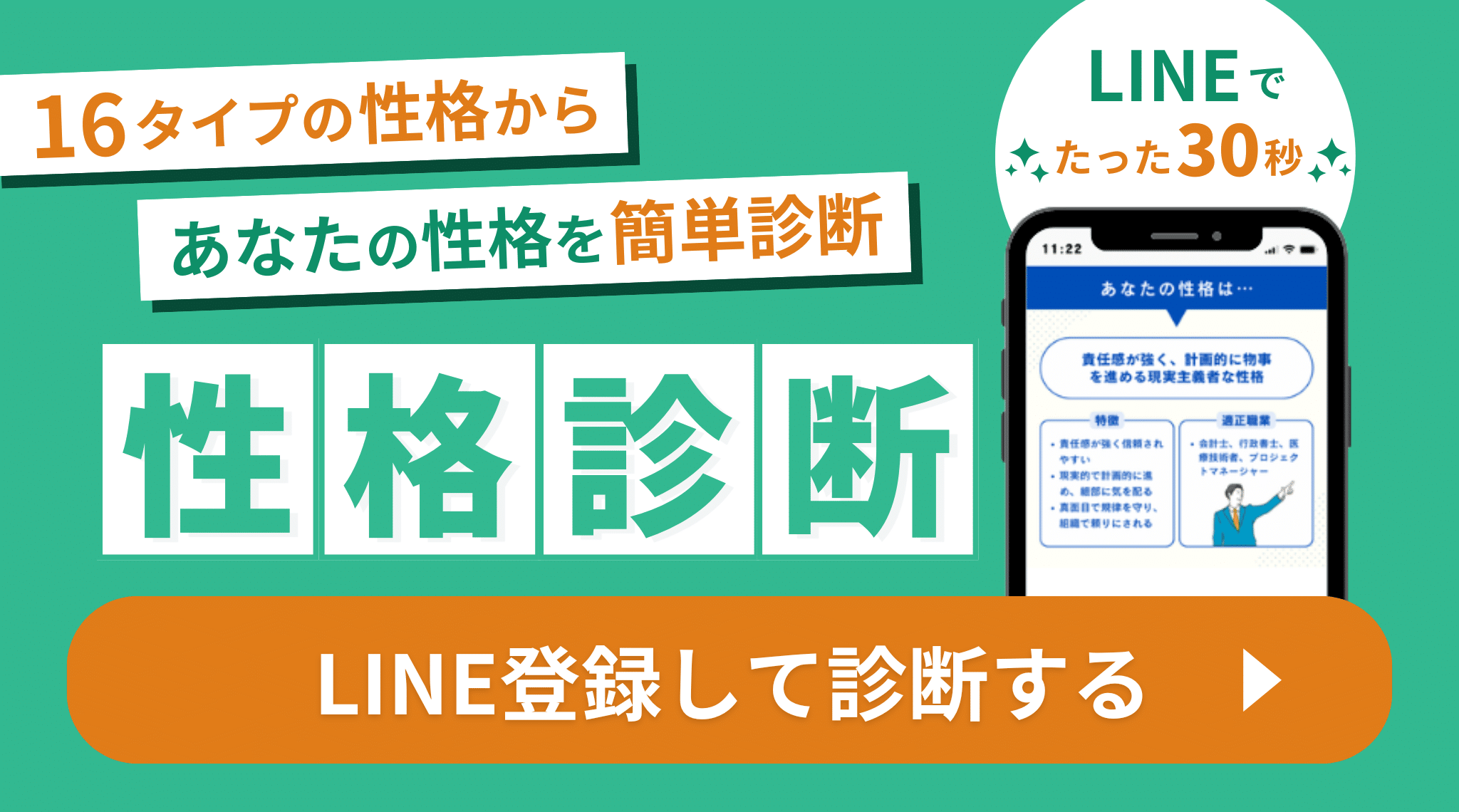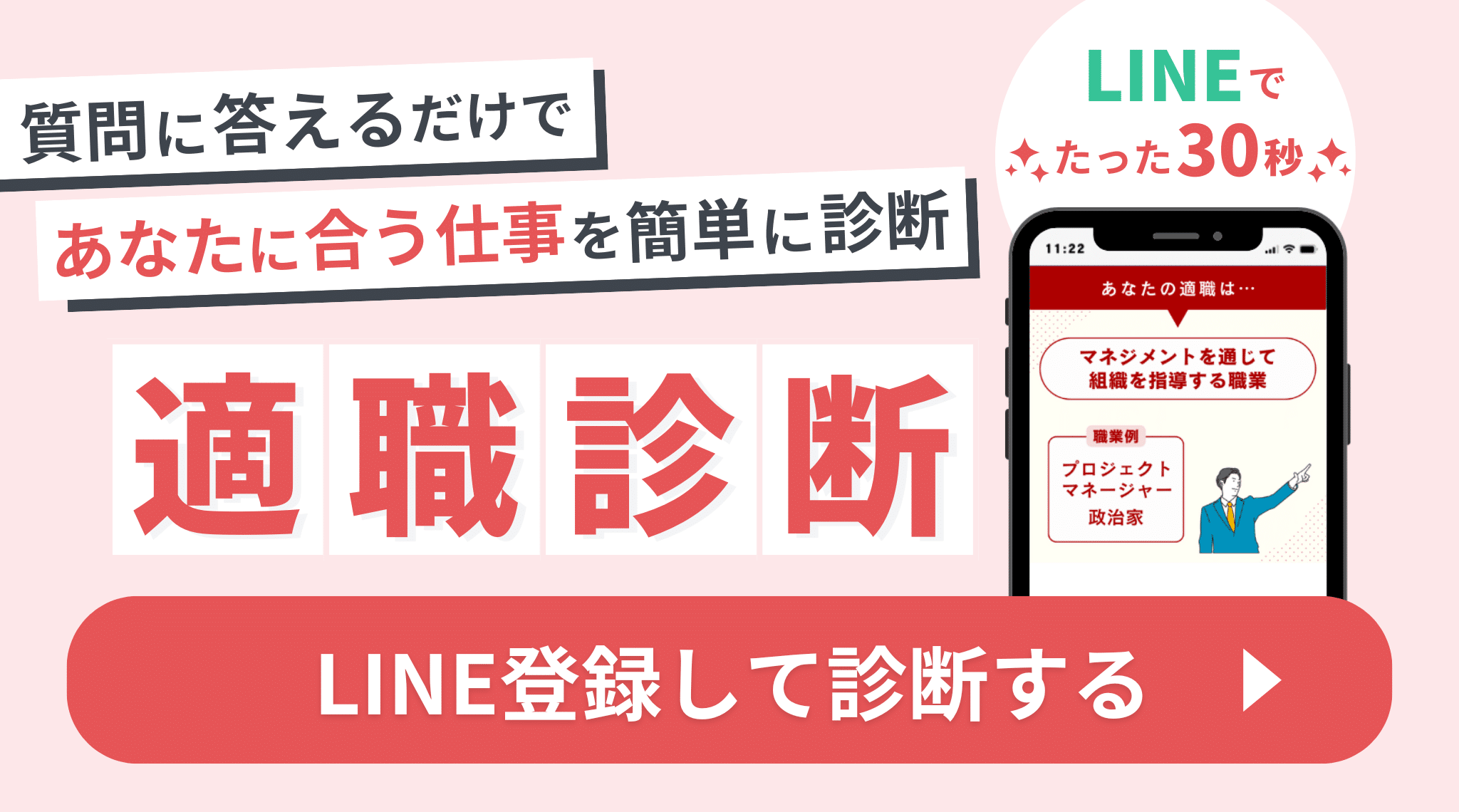自分史を作成するメリットと書き方、ポイントについて解説
2024/8/15更新
はじめに

本記事は、自分史について詳しく知りたい就活生向けです。
希望する企業の選考を通過するために、必要な自分史の作成方法を解説しています。
とくに、自分史を作成するメリットや手順、例文など、わかりやすく説明していきますので参考にしてください。
- 自分史とは?
- 自分史の書き方がわからない
- 自分史を作成するポイントが知りたい
自分史について理解することで、効果的に就活が進められるでしょう。
ぜひ最後までお付き合いください。
4泊5日の上京就活を応援!満員御礼の就活イベントを今年も開催!
宿泊費完全無料、東京までの交通費補助で負担を減らせます!
最大25社の優良成長企業と就活仲間に出会えるので、今から就活する学生は必見です!
あきらめないで!25卒も優良企業に出会えるチャンス!
夏採用に動き出す首都圏の優良企業を、就活ハンドブック独自にご紹介!
次こそうまく進めたい就活生に、専任のキャリアアドバイザーがつきます。
ぜひ、いまの不安をぶつけてみてください!
二人三脚で就活をサポートするので、就活をやってこなかった人も必見です!
就活生に人気のコンテンツ
完全無料
自分史とは
自分史とは、自分の人生を振り返り、時系列順にまとめたものです。
自己分析する方法の1つとされています。
企業は、就活生が提出した自分史を参考に、就活生の価値観や性格などを把握しようと考えているでしょう。
そのため、就活生は学生時代の体験や、経験を思い出し、わかりやすくまとめることが大切です。
企業によっては、自分史とは表現しないものの、同じような意味で使用している場合があります。
自分の希望する企業の選考フローになくても、自分自身について深く理解しておくことで、エントリーシートの作成や、面接でも効果を発揮するでしょう。
自分史を作成する3つのメリット

就活生が自分史を作成するメリットは、以下の3つです。
- 自分の大事にしている価値観が見えてくる
- 課題にぶつかった時の行動パターンがわかる
- 面接官に自信を持って、自分をアピールできる
自分史を作成することで、自分の価値観や、行動指針などを客観的に認識できるでしょう。
その結果、エントリーシートの作成や面接にも有効です。
自分史を作成するメリットが知りたい就活生は、ぜひ参考にしてください。
?自分の大事にしている価値観が見えてくる
メリットの1つ目は、自分の大事にしている価値観が見えてくることです。
具体的な方法については後ほど詳しく触れますが、幼少期から大学時代までに起こったエピソードを全て洗い出してください。
人は誰でも、付き合う人や周囲の環境によって価値観や考え方が、少しずつ変わっていきます。?
「昔は熱血な人は苦手だったけど、今はそうでもなくなった」
「昔は柑橘系の食べ物が好きだったけど、今はあまり好きではなくなった」
などです。
価値観の変化は、生きている限り当然のことなのでしょう。 しかし、“昔からずっと変わらない” ものも存在します。
それが、「自分の中で、ずっと大切にしている価値観」です。
例を挙げて考えてみましょう。
Aさんは、家の裏に公園がある自然豊かな環境で育ったとします。
幼少期から、身の回りに自然があることが当たり前でした。
大学進学を機に上京し、Aさんは自然と触れ合う機会が少なくなってきました。
しかし、疲れた時に”なぜか”無性に公園に行きたくなります。
さらにゲームやカラオケといったインドアな過ごし方よりも、キャンプやバーベキューなど自然を感じられるアウトドアの方が、気分転換になると感じました。
Aさんは、こうした「自然の中に身を置くこと」は、無意識のレベルで好んでいます。
幼少期から「自然と触れることの楽しさ」を知っていたからであり、Aさんは「自然への思い」を “ずっと変わらない価値観” として抱いていると予想できるでしょう。
上記のように、幼少期の環境と今の自分を照らし合わせることで、自分が今抱いている価値観は、人生のどこに根を下ろしているのか、あらためて理解できます。
?価値観については、以下のページに一覧が掲載されていますので参考にしてください。
課題にぶつかった時の行動パターンがわかる
2点目は、課題にぶつかった時の行動パターンがわかることです。
人生山あり谷ありというように、これまでの人生が順風満帆であった人は、そうなかなかいません。
何かしらの壁にぶつかり、自分なりの方法で乗り越えてきたからこそ、今があるのです。
自分が苦しかった時、しんどかった時の原体験を思い出す作業はなかなか難しく感じるかもしれません。
しかし、就活を機に「自分史」という形であらためて書き出してみると、「自分がその時どのように感じ、何を課題として捉え、どのような方法で解決に至ったのか」について、客観的に理解できるでしょう。
以下は、例になりますので参考にしてください。
Bさんは「留学中、全然コミュニケーションが取れない」という課題にぶつかっていました。
その対処法として
・毎日の会話の中で、わからなかった単語を書き出し毎日意味を調べる
・たとえ仲の良い友達がなかなか出来なくても、イベントに参加してみる
など、粘り強く繰り返していた結果、Bさんは次第にコミュニケーションが楽になっていきました。
また、Bさんが思い返してみると、大学受験の時の勉強も、毎日コツコツ粘り強く取り組むことにより、第一希望に受かっています。
上記から考えると、Bさんが課題にぶつかった時の行動パターンは「粘り強く、泥臭く継続して努力する」です。
上記のように過去苦しかった時のエピソードと、「当時どのようにして乗り越えたか」について見ていくことで、自分の行動パターンがわかってきます。
実体験に基づいているので、自己PRの材料として非常に有効でしょう。
面接官に自信を持って、自分をアピールできる
最後のメリットは、面接官に自信を持って、自分をアピールできることです。
時系列に沿ってエピソードを深掘りしていくことで、自分のこれまでの人生、また自分という人間について納得感を持って理解できるようになります。
これまで「なぜ自分は〇〇がこんなに気になるんだろう」「なぜ自分は人と違う価値観を持っているのか」など、よく理解できずにいた部分も理解できるようになり、自分という人間について、より客観的に捉えられるようになります。
つまり、過去を改めて振り返り、言語化することで、今まで自分でも気がついていなかった自分自身のことが、見えてくるかもしれません。
そして、自分が大切にしている価値観や、課題にぶつかった時の乗り越え方について真に理解することは、自分への納得感、ひいては人生への自信につながります。
自分史を作成することで自己分析を深めることが可能です。
さらに、深めた自己分析を整理し落とし込むことにより、他者へより分かりやすく自分について伝えられるようになります。
過去の経験に裏付けされた言葉は、そうでないものよりも説得力があるでしょう。
面接官にも、自信を持って自己アピール出来るようになります。
自分史作成の3つの手順

それでは、実際に自分史を書き進めてみましょう。
流れは以下になります。
- 時系列順にエピソードを書き出す
- 深く掘り下げる
- 他人に見てもらう
手順を理解することで、スムーズに自分史の作成に必要な情報が集められるでしょう。
時系列順にエピソードを書き出す
まずは、過去の出来事・エピソードを時期ごとに、項目を分けて書き出してみる方法です。
時期としては、幼少期、小学校、中学校、高校、大学と分けて、項目別に書き出してみましょう。

または、下記のような形でジャンル別に分けても、わかりやすいです。

あくまで一例であり、書き出す項目は自由ですが、以下に例を示すので困った時は参考にしてください。
- 印象に残っていること
- 時間を使ったこと
- 頑張ったこと
- 楽しかったこと
- 辛かったこと
- どんな友達と仲が良かったか
- 自分から率先して行ったこと
- どんな教科・講義に力を入れたか
- 何か大きな失敗をした出来事があるか
- 海外へ行くなどの一大イベントはあったか etc.
以上に挙げたような項目を、志望企業や業界別に適したものを選択し、それぞれの時期ごとに書き出してみましょう。
この時点では、「思いつく限りたくさん書き出し、エピソードを漏れのないように把握する」ことが目的ですので、重複したり、複数になったりしても問題ありません。
細かく書き出せば出すほど、自分史の精度は高くなります。
それぞれの項目において出来事の共通点や項目間での相違点をまとめる
先ほど整理したことを、さらに共通点や項目間での相違点をまとめ、深掘りしていきましょう。
まとめることで冒頭で挙げた「自分が大切にしている価値観や、課題にぶつかった時の行動パターン」が明確になります。
共通点でまとめると、自分がある環境下ではどのように反応したり、行動したりするのか明確になるでしょう。
さらに、それぞれの出来事について「なぜそう考えたのか」「なぜその行動をとったのか」「何が変化したか」など掘り下げて考えていくと、自分の大事にしている価値観が見えきます。
また、項目間の相違点や、時期によって変化したことをまとめることで、ある一面からだけではなく、多面的に自分を見つめられるでしょう。
たとえば、小学校の時は人見知りだったためよく1人で遊んでいたが、大学では社交的になり友達が大勢できた、という変化があったとします。
環境の影響もあるでしょうが、それ以上に自分の考え方の変化やいずれかの経験によって変化した、とも考えられます。
自分の価値観や行動・思考パターンを分析していくと思いもかけない発見があるかもしれません。
とくに印象的なものや思い入れのあるエピソードは、面接でも話しやすいので、自分を第三者的に捉え、深掘りしてみましょう。
家族や知人にも見てもらう?
家族や知人にも見てもらうことも重要です。
ちょっと恥ずかしく、勇気がいることかもしれませんが、もし可能なのであれば、ぜひ自分をよく知る友人知人・家族にも見てもらいましょう。
自分だけでエピソードを洗い出そうとすると、どうしても偏ったエピソードになりがちです。
とくに、親は自分のことを幼少期から知っている貴重な存在であり、幼少期の様子や、些細な変化についても鮮明に覚えています。
可能であれば、ぜひこの機会に聞いてみましょう。
【例文あり】自分史の内容を面接でアピールするには?

ここまで、自分史のやり方について解説してきました。
本項では、面接で具体的に自分史の内容をアピールする方法について、例を挙げながら見ていきます。
例文:「留学を機に語学を猛勉強、TOEICスコアが250点も上がった」
「幼い頃から好奇心旺盛な性格で、何か自分の知らないことについて学ぶことが好きでした。
中学で英語というツールを身につけてからは、英語を皮切りに、どんどんと海外にのめり込むようになりました。
学校の英語コンテストでも優勝し、学部は語学系に進みました。
それまで「自分は結構語学ができる方だ」と思い込んでいたのですが、留学先で、自分が全然話せず、コミュニケーションが取れないことにがく然としました。英語系の学部なのに、ろくに話せないのが本当に悔しくて、帰国後も英語漬けの環境を維持できるよう努力しました。
常に英語の洋楽やBBCなどのポッドキャストを聞き流し、どんなに忙しくてもスカイプ英会話で毎日英語を30分間話す、というのを、粘り強く半年間継続しました。
その結果、TOEICのスコアが留学前と比べて、250点も上がっており、ネイティブと話すことに全くストレスを感じなくなっていました。
将来も「時間はかかっても、コツコツと努力することで目標を達成する」を意識し、さまざまな課題に取り組んでいきたいです。
ちょっと冗長的な印象もありますが、「逆境をバネに、根気強く努力できる人材である」ということがアピールできます。
文章に落とし込む際には、モチベーショングラフを意識し、これまでの人生で一番凹んだことや悔しかったこと、今の自分の原点になっていると思うことを考えながら書いていきましょう。
文章にメリハリが出て、読んでいる方も飽きずに、最後まで読んでくれるはずです。
自分史は、ただ作成するだけでは意味がありません。
面接官を納得させるために、わざわざ自分史を用いて自己分析するので、作成自体を目的とするのではなく、何のために作成するのかを頭に入れておきましょう。
ちなみに、モチベーショングラフについて、書き方など詳しいことは以下の記事内で紹介しています。
余談ですが、企業によっては選考過程で簡単な自分史や、それに似たモチベーショングラフの提出を求められることもあります。
提出の意図は、作成の目的と似ており、企業が求める人材像と就活生の価値観や、過去の経験がマッチしているか判断するためでしょう。
自分史は、企業にとっては大切な判断材料となるため、しっかりと作成しましょう。
ESで自分史の提出を求められたら?

自分史の提出を求められたら、問われていることをしっかりと理解したうえで、自分のアピールしたい価値観に沿って記載することが大切です。
書類選考においては、履歴書と同様にES(エントリーシート)の提出を求められることがあります。
エントリーシートの場合、文字制限もあるため、自分史すべてを書くわけにはいきません。
企業が見ているポイントをしっかり理解し、適切に記載しましょう。
企業が見ているのは、主に以下の3つです。
- 学生の過去の経験
- それに基づいた能力や人柄
- 仕事への適性があるか
上記に沿って話すことで効果的に面接官にアピールできるしょう。
大枠としては、アピールしたい軸を決め、それを裏付ける経験(自分史)をそろえて記載します。
自分の人柄や能力を自分史を通じて示し、なおかつ、志望する企業や職種への適性もアピールする必要があるのです。
過去の経験をたくさん書き出して作成した自分史ですから、さまざまな面があるはずです。
その中から適切な経験を抽出して、記載しましょう。
さらにアピールしたい場合は、エントリーシートで取り上げた経験について、行動した理由や、過程で心がけたことなども示すとより効果的です。
自分史の作成に行き詰まった時の2つの対処法

自分史の作成に行き詰まった時の対処法を2つ紹介します。
自分史を作成するうえで、過去の出来事を振り返っていると、どうしても途中で行き詰まったり、落ち込んだりしてしまうこともあります。
適切な対処法を理解しておくことで、素早く立ち直れるでしょう。
家族や、自分を知る周りの人に話を聞いてみる
自分史の作成に行き詰まった時は、家族や自分を知る周りの人に話を聞いてみることがおすすめです。
いくら自分で思い出そうと頑張っても、忘れてしまっていることももちろんあります。
そんな時は、他者の力も借りましょう。
自分をよく知る家族や友人に話を聞いてみることで、忘れていたできごとも思い出せるかもしれません。
また、他者の力を借りることで、自分がそれぞれのできごとに対して、どのように取り組んでいたのかを、客観的に知ることができます。
たとえば自分では「普通」だと思っていることでも、他の人からすれば「なかなかまねできない素晴らしいこと」と思われている可能性があります。
反対に、自分では長所と考えていても、長所と呼ぶには弱いこともあるでしょう。
自己分析が独りよがりの結果にならないためにも、他者の力を借りることは有効です。
自分の昔のSNSをみてみる
X(旧Twitter)やFacebookなど、SNSのアカウントを持っている就活生は自分のSNSをさかのぼってみるのも1つの手です。
SNSには、その時感じた感情を発信している可能性が高いので、当時の記憶がありありとよみがえってくるかもしれません。
「過去の投稿は、もう消してしまった」という人も多いかもしれませんが、思い切ってぜひ確認してみましょう。
まとめ

自分史を作成するのは、時間と手間がかかります。
しかし、就活において、自分の過去の経験を振り返る作業は必要不可欠です。
自分史を作成し、自分自身を細部まで理解することで、面接官に自分の強みを分かりやすく伝えられます。
架空のことを書いたり、意図的にできごとをなかったことにすることは避けましょう。
選考過程で、自分を必要以上に良く見せる必要はありません。
仮に面接で突っ込まれ、ボロが出てしまい結果後悔するのは自分です。
嘘の自分史を提出するデメリットが大きいためやめましょう。
確かに、過去を振り返ることは、あまり気の進まない作業かもしれません。
中には、恥ずかしくて思い出すのがおっくうなできごともあるかもしれません。
しかしそこに、自己分析のヒントが眠っているのです。
もちろん無理をする必要はありませんが、これを機に素直な自分と向き合ってみることをおすすめします。
誰ひとりとして、全く同じ過去を持っている人はいません。
自分らしさを存分にアピールして、納得のいく就活をしましょう!