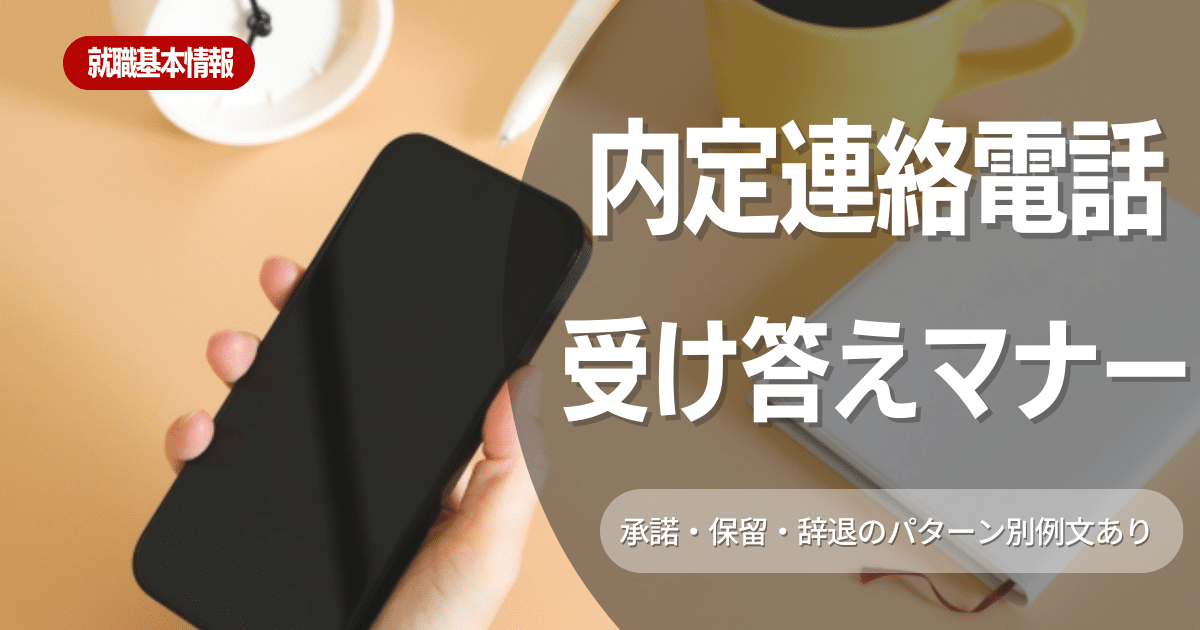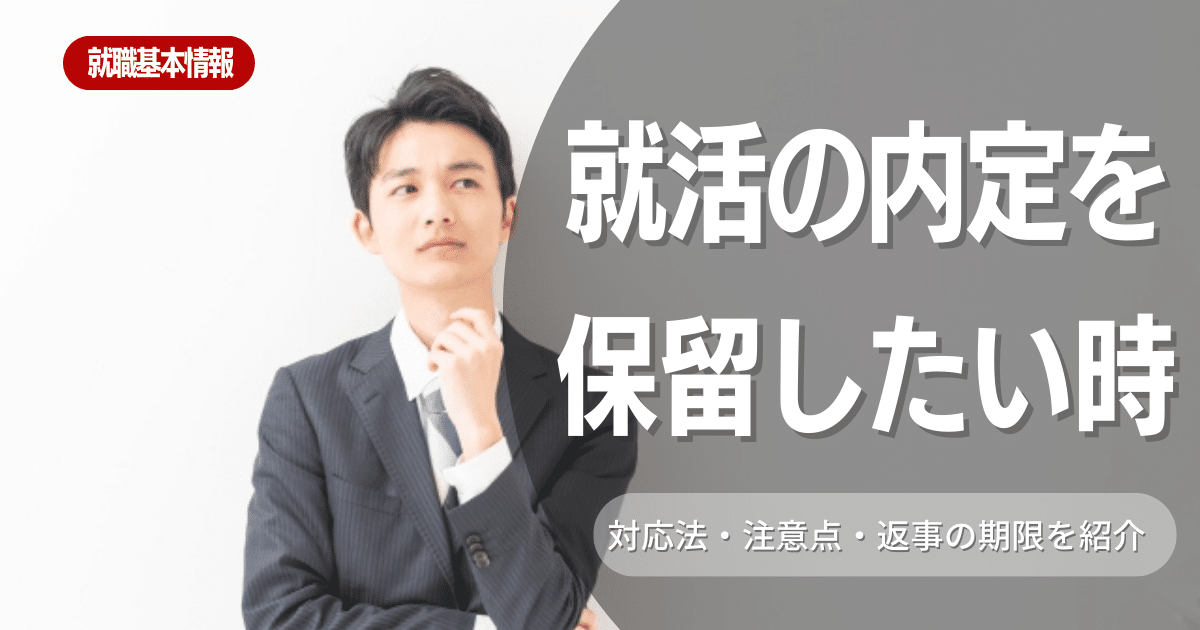内定承諾後の辞退は可能?伝え方やトラブル回避のコツを解説
2024/10/21更新
はじめに
内定承諾書を提出した後に「やっぱりほかの企業にしようかな…」と思い内定を辞退しようか迷ってしまう方も少なからずいるようです。
しかし、果たして内定承諾後の辞退は可能なのでしょうか?
もし承諾後に辞退するとなると、企業からの印象が悪くなったりもめたりしないか心配ですよね。
そこで本記事では内定承諾後に辞退してもいいのか、辞退の際のマナーや注意点について解説します。
以下のようなお悩みのある学生は必見ですので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- 承諾書を提出したあとに辞退できるか知りたい
- 承諾後の辞退の伝え方が分からない
就活生に人気のコンテンツ
完全無料
上京を志す地方学生ならジョーカツ!
あなたのキャリアを加速させるチャンス!
無料で利用できる快適な個室シェアハウス、
東京までの交通費サポート付き
首都圏の注目企業への就活ならジョーカツ
首都圏の学生ならスタキャリ!
理想のキャリアを実現へと導く第一歩!
あなたにピッタリのキャリアアドバイザーを選び、
自分にマッチする優良企業をご紹介
首都圏企業のES添削から面接対策まで、就活ならスタキャリ
内定承諾後に辞退は可能?

結論からいうと、入社する2週間前までの辞退であれば、内定承諾後であっても法的に問題はありません。
マイナビが2019年9月、20卒を対象に採用活動を行った1,349社を対象とした調査によると、内定辞退率が「3割以上」の企業は全体の53.1%(前年比2.9%減)にものぼります。
企業側も内定した学生全てが入社してくれるとは思っておらず、一定数の内定辞退はやむを得ない、と踏んでいます。
ただし、内定承諾書の提出前か後かどうかで、その難しさは変わってくるでしょう。
内定承諾書の提出後ですと、企業側としては「絶対に入社してくれる」という確信の元に準備を進めています。
承諾書を提出したあとの辞退では、トラブルに発展する可能性もゼロとは言い切れません。
もちろん「法的に問題はない」ですし、内定辞退も立派な権利の一つであることには間違いないでしょう。
しかし、企業が一人当たりの採用コストとして数十万、数百万円の費用をかけていることは、忘れてはいけません。
「先方に迷惑をかけてしまっている」という自覚を十分に持つことが大切です。
それでも内定を辞退するのであれば、せめて伝え方や言葉選びには最大限配慮し、謝罪の姿勢を持って先方からの理解を得られるように努めることが重要です。
内定承諾書の提出したあとの辞退でも大丈夫?
結論からいうと、内定承諾書を提出したあとでも、辞退することはできます。
内定承諾書は契約書としての側面もありますが、法的な拘束力はないからです。
学生にとっては「春からは御社に入社して働きます、内定を受け入れます」という宣誓書のような書類にあたります。
企業は内定を出した就活生に対し内定を取り消すことはできませんが、内定者には内定を取り消す権利が認められています。
入社することは双方の確認があってできるものであって、一方がしたくないと言っているのに強制力を持たせて入社させることはできないのです。
やむを得ない事情であれば仕方ありませんが、しっかりと考えた上ですることがマナーであり、適切な対応であると言えるでしょう。
内定承諾後に辞退をするときに知っておきたいこと
内定承諾後の辞退は法的には問題ないため、辞退しやすいと考える人もいるかもしれません。
しかし、よく考えず辞退すると後悔することもあります。
以下では内定承諾後に辞退をするときに知っておきたいことを解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 企業は莫大な採用コストと時間をかけている
- 辞退した企業と今後かかわる可能性もある
- 軽率に判断して後悔することがある
企業は莫大な採用コストと時間をかけている
企業は学生を採用するにあたり、莫大な採用コストと時間をかけて内定を承諾してくれています。
内定承諾後の辞退は企業の人員計画を狂わせてしまうことになるので、多大なる迷惑をかけかねません。
「辞退すればその後は関係ない」と思わず、企業側の事情も汲み取ることが大切です。
辞退した企業と今後かかわる可能性もある
内定を辞退したらもうその企業との関係はおしまい、と考える方も多いかもしれません。
しかし、実際はほかの企業に入社後にその辞退した企業とかかわりを持つ可能性もあります。
もしマナーのない辞退をしてしまうと、今後かかわるときに会社全体の印象を悪くしてしまうかもしれません。
いつどんな時でも辞退した企業の社員と堂々と会えるように、誠意を見せましょう。
軽率に判断して後悔することがある
内定辞退しづらいからといってそのまま入社してしまったり、他の企業の方がなんとなくイメージ良いからそっちに行こうと軽率に判断したりするのはNGです。
自分の納得いく就活をするためにも、なぜ自分は内定承諾を辞退したいのかしっかり言語化できるようにしておいてください。
内定承諾書後に辞退するリスク
内定承諾後に内定を辞退すると、思わぬトラブルに発展することもあります。
以下では内定承諾書後に辞退する2つのリスクについて解説するので、これらのリスクがあることをふまえて辞退するか考えてください。
- 損害賠償が発生することもある
- 再応募できないことがある
損害賠償が発生することもある
入社より2週間以上前に内定辞退の旨を伝えている場合は法的には何も問題ありません。
しかし、入社を前提に会社の経費でスキルアップ講習などを受けていた場合は、費用返還を請求されるかもしれません。
入社日まで2週間を切った後の辞退はすでに名刺や制服などを発注するなど費用が発生していることが多いです。
そのため、ギリギリの辞退は損害賠償が発生する可能性があることも念頭に置いておきましょう。
再応募できないことがある
「1年以内の再応募は不可」といった規定がない場合、内定を辞退しても再応募することは可能です。
しかし内定承諾後の辞退はあなたに対するイメージが低下している可能性が高いです。
ほかの入社への意欲がある学生を優先的に選ぶこともあるので、基本的には再応募できないことを前提に辞退するかどうか考えましょう。
内定承諾後に辞退する旨を伝える際の6つの注意点

いろいろと思い悩んだ結果、「内定を辞退しよう」と決意したとします。
しかし、なんといっても難しいのは人事への伝え方ではないでしょうか。
内定先の企業は「入ってくれると思って内定を出している」わけですので、相手の気分を害さないよう、最低限のルールやマナーを守って伝えるのが礼儀です。
ここからは、伝える際の流れと注意点について解説していきます。
- 決めたら早めの連絡
- タイムリミットは入社の2週間前
- 誠実に対応し、決して嘘はつかない
- 辞退理由はあくまで「自己都合」
- 最後までしっかりと考える
- 伝える手段は電話+詫び状
決めたら早めの連絡
内定の承諾を辞退しようと決めたなら、なるべく早めの連絡を入れるべきです。
先ほども説明したように、企業は内定の承諾をしている場合は「入社するもの」として就活生をカウントしています。
もし仮に入社する人数が一人でも少なくなってしまえば、その後の営業に多大な影響が出てくるでしょうし、また新たに人を採用する活動をしなければなりません。
したがって、もし「内定を辞退」しようと決めたならば、早めに人事の担当に話をするべきです。
タイムリミットは入社の2週間前
早く連絡しなければいけないと思っていても、最後まで悩んでいてどうしようと考えていることもあるでしょう。
その場合、最低でもどれくらいまでに内定の辞退の連絡をすればいいのでしょうか。
法的に定められている範囲では、労働者の権利として「入社の2週間前」までは可能とされています。
つまり逆を言えば、どのような理由があろうとも、2週間を切ると辞退はできません。
しかし、実際に2週間前に内定辞退をしてしまうのはギリギリすぎますし、先方にとって大きな損害となります。
相手の怒りを買わず、穏便にすませたいのであれば、目安として遅くとも1ヶ月くらい前までに連絡するようにしましょう。
1ヶ月前くらいに連絡できれば、先方企業もなんとか計画を立て直せるはずです。
だからと言って「じゃあ、1ヶ月前に連絡すれば良いや」という訳ではありません。
社会人らしく礼儀と節度を持って、決めたのであれば責任を持ち、なるべく早く先方に伝えるようにしましょう。
誠実に対応し、決して嘘はつかない
感情的になってしまったり、やっつけで連絡をしてしまったりしてはいけません。
就活生は内定をもらっている時点で、学生ではなくいち社会人として見られています。
ですので、そのように「社会人として」自覚を持ち、冷静に対応するべきです。
就活生の中には、内定承諾辞退の理由を嘘で固めようとする方もいますが、これはよくありません。
企業の人事は何万人と就活生、社会人と接してきていますので、嘘はかんたんに見抜いてしまいます。
お互い後味が悪くなりますし、嘘を付いていると思われればスムーズに内定を辞退することが難しくなってしまいます。
話をこじらせないためにも、内定を出してくれたことに感謝の気持ちを忘れず、最後ぐらいは誠実に行動するようにしましょう。
辞退理由はあくまで「自己都合」
企業の中には、辞退理由を聞いてくる場合も少なくありません。
他の企業へ乗り換える場合、本音を言えるはずがありませんし、悩ましいところですよね。
このような場合は、「他社から内定を頂きましたが、熟考の末、私の長所は〜のような環境であればより活かせるのでは、と感じた」と切り出しましょう。
理由はあくまで自分主体であることを明確にしてください。
間違っても、「あちらの方が待遇が良かった」「残業時間が少なかった」など、あとあと関係性がこじれかねないような、否定的な表現は避けましょう。
最後までしっかりと考える
一度は内定を承諾したということは、その企業に魅力を感じて、承諾に至ったわけです。
内定の辞退はかんたんにできますが、それまでの時間や努力がないものになってしまいます。
また、内定承諾を辞退してしまうとその後「やっぱり撤回して、入社したい」と思い直しても、企業が取り合ってくれるはずがありません。
当然、企業も内定者に期待して、戦力の一人として考えています。
採用コストもかかっていますし、今後の企業戦略にも関わってきてしまいます。
なので、最後まで「本当に内定の辞退をしたいのか?しても後悔しないか?」を突き詰めて考えておくことが大切です。
伝える手段は電話+詫び状
内定を辞退すると決めたら、どのような手段で連絡をしたらいいのでしょうか?
結論から言うと、まずは電話で連絡をし、その後「詫び状」と呼ばれる手紙を書くと良いでしょう。
ビジネスのシーンにおいては、「重要なことは必ず直接伝える」というルールがあります。
何か謝罪をする際は、電話で行うのが一般的でしょう。
メールや手紙のような文字の連絡手段だけでは、こちら側の謝罪の姿勢が相手に伝わりづらいです。
電話の声色から、こちらが本当に申し訳なく思っていることが相手にも伝われば、相手も気分を害してトラブルになる可能性も少なくなるかもしれません。
ちなみに、メールで先に連絡をすることは
- 自分の思考を整理することができる
- 相手に内容を正確に伝えることができる
というメリットもあります。
しかし、一方的な印象が強く、こちら側の誠意をくみ取りづらくなることもあります。
メールでの内定辞退は、何度かけても電話がつながらないときに限定しましょう。
そのあと、必ず電話でフォローの連絡を入れることを忘れないでください。
内定承諾後に辞退する際の例文【電話・メール・詫び状】

続いて、電話(メール)・詫び状にて、実際に内定辞退を伝える際の例文について見ていきます。
せっかく内定を出してくれた企業を断ることは、誰でも気が引けるものです。
ですが、いつまでも先延ばしにすると、企業とのトラブルになりかねません。
内定をもらったことへのお礼を述べた後は、結論ファーストですぐに内定辞退の話題を持ち出し、こちら側の意志の強さを提示することが重要です。
【電話】内定承諾後の辞退を電話で伝える場合
お忙しいところ恐れ入ります。
先日内定承諾をさせていただきました、○○大学の□□と申します。
大変恐縮ながら、やはり入社を辞退させて頂きたいと思い、連絡させていただきました。
ご担当の○○様はいらっしゃいますでしょうか?
…
大変心苦しいのですが、〇〇のため、
内定辞退をさせていただきたく、ご連絡させていただきました。
一度内定をいただきながら、辞退を申し上げるなどと多大な迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
何卒お許しいただきたくお願い申し上げます。
繰り返しにはなりますが、理由は嘘をつかず、正直に答えることが肝要です。
電話は緊張しますが、最後まで誠実な態度で臨めば、先方にもわかってもらえるはずです。
相手を否定することは決してせず、あくまでこちら側の自己都合であることを伝えた上で、しっかりと事前に準備をして臨みましょう。
円満に内定辞退をするための対処法については以下の記事で紹介しています。
【メール】内定承諾後の辞退をメールで伝える場合
件名:内定辞退のご連絡/○○大学○○学部○○○○
○○株式会社人事部人事課
採用担当○○様
お世話になっております。
○○大学○○学部ジョーカツ太郎と申します。
この度は内定のご連絡をいただきまして、誠にありがとうございます。
内定をいただいたにもかかわらず誠に恐縮ですが〇〇のため、大変非常識ではございますが貴社への入社を辞退させていただきたく、ご連絡を差し上げました。
貴重なお時間を取って頂いたにも関わらず、このようなお返事となり大変申し訳ございません。本来なら、直接お会いしてお詫び申し上げなければならないところ、メールでのご連絡となりますことをご了承いただきたくお願い申し上げます。
採用に関わってくださった皆様には大変お世話になりましたことを、心より感謝しております。
末筆ながら、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
―――――――――――――――
ジョーカツ太郎(ジョーカツ・たろう)
○○大学○○学部○○学科○年
携帯電話:080-☓☓☓☓-☓☓☓☓
メール:jokatsutaro@☓☓☓☓☓☓.co.jp
―――――――――――――――
メールで伝える場合は、このような形が良いでしょう。
確かに内定辞退は学生の権利ですが、迷惑をかけたことは事実ですから、謙虚な姿勢を示すことが重要です。
署名とタイトルにも、誤字脱字などの間違いがないか気をつけましょう。
メールでの辞退のマナーや書き方についてはこちらでくわしく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
【詫び状】の書き方
拝啓〇〇の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度は貴社の採用内定をいただき、誠にありがとうございました。
電話でもお話させていただきましたが、大変非常識ながら内定を辞退させていただきたくご連絡いたしました。
最後まで悩みましたが、自身の適性などを熟慮した結果、誠に勝手ながら他の企業への入社を決意いたしました。
貴社の皆様には、お時間を割いて選考をして頂いたにも関わらず、期待にお応えすることができず誠に申し訳ございません。
末筆ではございますが、貴社ますますのご発展をお祈り申し上げます。
敬具
令和◯年◯月◯日
ジョーカツ太郎
〇〇株式会社人事部
〇〇〇〇様
「詫び状」と記すと、仰々しく思えるかもしれませんが、内容としてはこの程度のもので十分です。
詫び状は、必ずしも送らなければならないものではありませんが、トラブルに発展するリスクを軽減させるためにも、送っておいて損はないといえるでしょう。
ポイントとしては、
- 内定辞退の意思
- 辞退の理由
- 辞退へのお詫び
- 選考への感謝
この4点が入っていれば十分です。
- 便箋は三つ折り
- 白無地+定型サイズの封筒に入れる(中身が透けないもの)
- 裏面の差出人の左上に「送付日」を記入する
これらのポイントを押さえ、最後まで丁寧な印象を残すようにしましょう。
内定承諾後に辞退した企業から脅されたとき時の対処法3パターン
内定を一度承諾したあとに辞退する行為は、企業にとっては不都合なできごとです。
企業によっては、内定を辞退することを不服に思い、就活生を脅すような行為に及ぶ場合もあります。
企業とのトラブルを避けるために、3つのパターンに分けて対処法を紹介します。
内定辞退は当然、リスクのある行動ですのでさまざまな噂が飛び交っているようです。
- 土下座を強要された
- 電話口でブチ切れられた
- 質問攻めにされた
- 辞退をやめるよう何度も説得された
こんな話を聞いたことがあるかもしれません。
実際、このような対応をされる企業など今時ほとんどありませんが、可能性はゼロではありません。
そもそも、ネット上で良い話は広まらず、悪い噂だけが尾ひれをつけて広まっていくものです。
もちろん、誰でも内定辞退の連絡をするのは怖いと感じるでしょうが、先延ばしにしてしまうと、企業にとってももっと都合が悪くなります。
できるだけ早めに連絡し、誠意ある対応を取り、納得してもらえるように努めることが大切です。
本項では、次のような脅しを受けた場合の冷静な対処法について解説します。
「損害賠償請求をする」と言われた場合
結論からいうと、内定承諾後の辞退であっても、就活生に損害賠償を支払う義務はありません。
前述の通り、内定承諾書に法的な拘束力はないありませんので、「内定承諾辞退」単体で見れば、訴えられる可能性も低いでしょう。
ただし、あまりにも入社ギリギリでの辞退だったり、企業側が非常に多額の資金を投入して入社の準備を進めていたりした場合は注意が必要です。
企業の信頼を損ねた、いわゆる「裏切り」行為とされ、損害賠償を請求されるケースもあり得ます。
とはいえ、訴訟されたとしても民法上では「解除」という扱いになり、学生側に支払い義務はありません。
もちろん、内定承諾辞退が企業にとって、好ましくない判断であることに変わりはありません。
ですが、内定辞退者に精神的ダメージを与えようと、名誉毀損を掲げ「スラップ訴訟」(嫌がらせ訴訟)をしてくる可能性もあります。
きちんと誠意をもって対応するようにしましょう。
「就職先に連絡して内定を取り消す」と言われた場合
冷静になって考えたいのは、そもそも先方がこちらの就職先を知っているかどうかです。
自分から明かさなければ知る由もありませんし、万が一、詮索して就職先がわかり、就職先にクレームが入ったとしても、それでどうなるというのでしょうか?
就職先から好感を抱かれており、信頼関係も構築できていたとすれば、たとえそのような連絡を受けたからといって、実際に取り消す企業はほとんどないでしょう。
このようなタチの悪い企業とは、今後関わりを一切切った方が賢明です。
また、このような企業体質であることを見抜けなかった就活生にも少なからず落ち度はあります。
逆ギレなど子どもっぽい対応は絶対に避け、大人の対応で乗り切りましょう。
「今後大学の後輩は全て内定を出さない」と言われた場合
よく考えれば、機会損失も甚だしいですよね。
優秀な学生と出会う機会を失ってしまいますので、実際にそのような行為におよぶ企業はほとんどなく、あくまで脅し文句であり、鵜呑みにする必要はありません。
もし仮に、本当に拒絶するようになったとすれば。「後輩に申し訳ない」と思うかもしれませんが、実際はその逆です。
このような企業から後輩が守られることになるわけですから、むしろありがたいことなのではないでしょうか。
これは、一つの捉え方にすぎませんが、このように構えておくのも手かもしれませんね。
内定承諾辞退に関するよくある疑問

内定承諾辞退の流れや注意点は理解できたものの、まだ少し不安を感じている方も多いかもしれません、
以下ではよくある質問を紹介するので、ここで辞退をする際の不安や疑問をすっきり解消させておきましょう。
内定後も就活を続けることはバレる?
内定先に少し不安が残る場合、期限まで待ってもらい、就活を続ける方が多いのではないでしょうか。
その後、うまく内定が出れば「内定承諾を辞退」ということになりますが、中には「内定が出たら就活を辞めると言ったのに、まだ就活を続けるとバレるだろうか」と不安に思う方もいるかもしれません。
こちらの回答としては、まずバレることはないでしょう。
リクナビやマイナビ上での選考状況は機密情報となるため、たとえ内定後に他社へエントリーしていたとしてもそれが外部に伝わることはありません。
もし、人事同士がつながっていたとしても、やはり人事戦略は社外秘の情報として扱われているために、外部に流出することはあり得ないでしょう。
外部への情報漏えいといった事態が起こってしまったら、会社の信用問題に関わってくるからです。
そもそも就活というものは、建前をつかって内定をもらうためのゲームのようなものです。
あまりにも正直すぎると、あとで自分がつらい思いをします。
ある程度は割り切る覚悟も必要でしょう。
内定保留の返答期限を過ぎたら「内定辞退」になる?
内定保留の返答期限を過ぎると、内定辞退扱いになることがほとんどです。
だからといって、企業への回答の電話を怠る行為はおすすめできません。
内定辞退になるだけでなく、あなたの在籍している大学まで評判を落としかねないからです。
「連絡を怠る」という行為一つで、あなたの大学の後輩が今後選考を受けられなくなってしまう可能性もあります。
かならず期限内には、内定保留への回答をするように気を付けましょう。
返送前の内定承諾書はどうする?
電話口で内定を承諾後、やっぱり気が変わって内定を辞退したくなった場合、手元には空白の内定承諾書のみが残るはずです。
このような場合、承諾書は企業の指示に従うようにしましょう。
通常、承諾書は「内定を承諾する」際のみ返送が必要になります。
ですので、承諾しない場合、返送の必要はない場合がほとんどです。
もちろん、企業によって対応方法は異なりますので一概には言えませんが、返送する場合は、添え状をつけて送るようにしましょう。
内定辞退後の再就職は可能?
「志望企業があって内定辞退をしたけれど、やはりよくよく考えたらあっちの会社の方が良かった。もう一度相談してみることは失礼だろうか」
状況によっては、このような境遇に置かれている方も少なくないかもしれませんね。
結論から言うと、残念ながら再就職は難しくなります。
よほど高い評価を受けていた場合や、辞退の際に引き止められていた場合は例外ですが、そうでない場合は、基本的に新卒としての就職は諦めた方が良いでしょう。
二次募集、三次募集を行っている場合、またゼロからのスタートとして書類選考から応募することは不可能ではありません。
しかし一度辞退しているという結果は残ってしまうため、選考の難易度は増す、ということは理解してきましょう。
エージェント経由の内定承諾も辞退可能?
中には、就活エージェントなどを経由して紹介してもらい、そのまま内定という形になる場合もあるでしょう。
もちろん、その企業にすんなり入社して問題がなければ良いのですが、第一志望ではないというケースも多くありますよね。
そのような場合、「せっかく紹介してもらったのに、内定辞退なんて失礼だし、そもそもさせてもらえるのだろうか」と、不安に思うのではないでしょうか。
結論を言えば、辞退は可能です。
もちろんエージェントにとっては、紹介料が入らなくなってしまうので嫌がられるでしょうが、エージェントも就活生の内定辞退には慣れているものです。
しっかりと誠実に理由を説明し、同様に理解を得られるように努めることが大切です。
さいごに
本記事では、内定承諾後の辞退について解説しました。
先ほども述べましたが、一度でも内定を辞退してしまえばそれで終わりです。
企業へ費やしてきた時間や努力が無駄になってしまいますし、何より先方企業にも迷惑をかけてしまいます。
内定承諾後に辞退するかどうかの判断は、慎重に行うようにしましょう。
ただし、本当に徹底的に考え抜いた結果、「内定を辞退した方が、自分の今後の人生にとっていい」と最終的に判断したようであれば、そのようにすべきです。
内定辞退のマナーを守って、企業側も就活生の皆さんも納得感を持って進み、後味が悪くないようにすることが大切です。