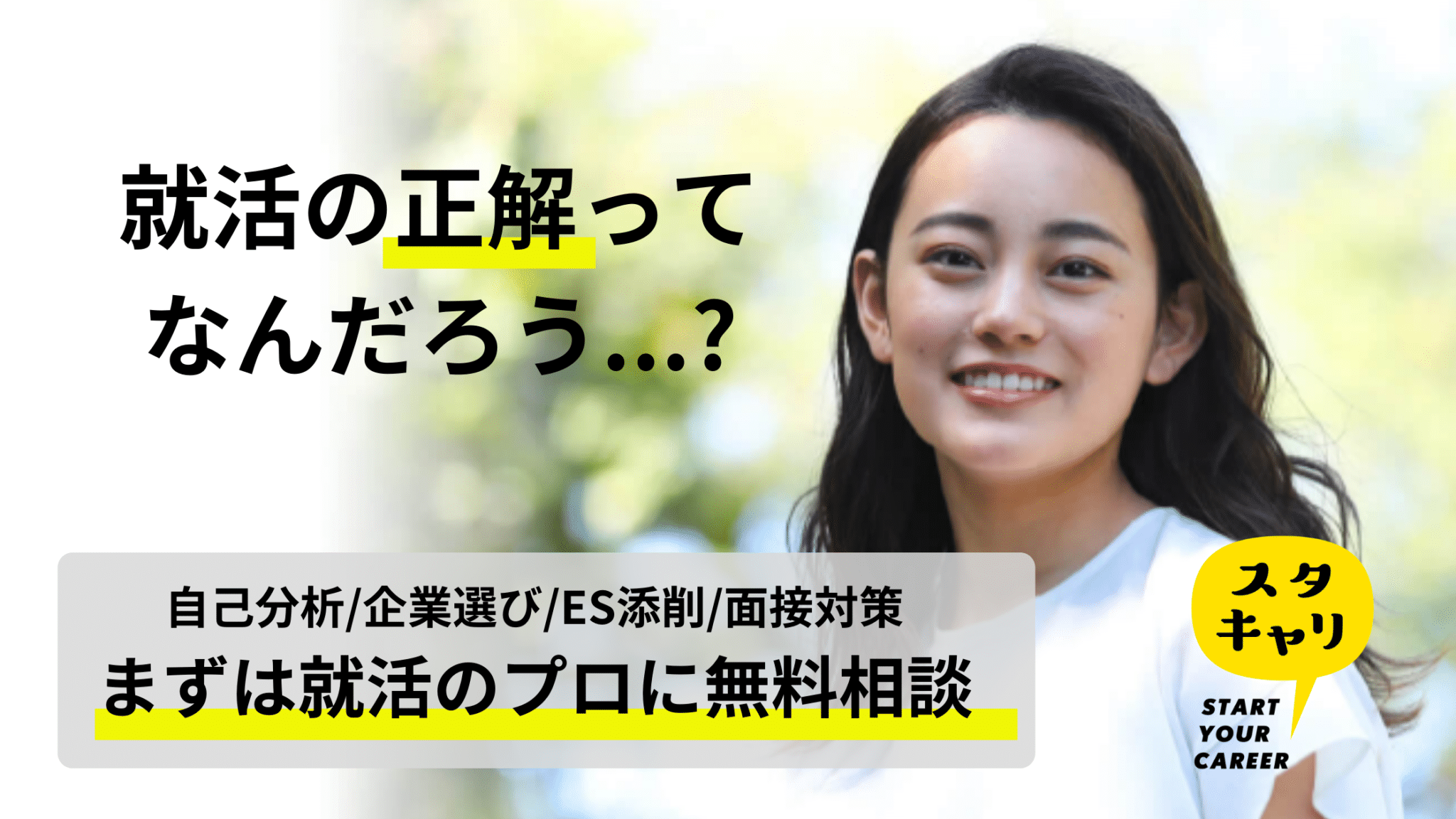面接が早く終わるのは不採用?評価されてる?合否の理由
2023年6月3日更新
はじめに
就活で面接が想定よりも早く終わると、不安になる学生は少なくありません。
手ごたえが分からず、落ちてしまったと落ち込んでしまうこともあります。
このように思い悩む時間が多いと、次の面接や説明会に向かう足が重くなってしまいがちです。
果たして面接が早く終わるのは、本当に不採用の証なのでしょうか?
この記事では、面接が早く終わる理由を、採用の場合と不採用の場合に分けてご説明していきます。
また、就活で重要な振り返りの方法や、面接が早く終わる時の対処法などもご紹介しています。
ぜひ不安を解消して、適切な対策を取れるようにしてください。
面接が早く終わるのは不採用?
面接が早く終わっても、必ずしも不採用が決まったわけではありません。
むしろ面接が早く終わるのはよくあることです。
理由は様々ですが、企業側の都合が存在する場合があります。
それは、候補者が想定よりも多かった場合や、もともと面接時間を長めに設定している場合が挙げられます。
企業は、借りた会場や使う人材の都合上、限られた時間内に全ての候補者の面接を行う必要があります。
候補者が多い場合は1人の面接時間を短くする他ありません。また、ある候補者が遅れてやってきた場合や、面接時間が長引いた場合に備えて、予定面接時間は長めに設定されているものです。
それによって、就活生側が想定しているよりも短い時間で面接が終わる場合があるのです。
このように就活生側になんの原因がなくても、面接が早く終わることはあります。
面接が早く終わる理由は?
面接が早く終わる理由として、企業側の避けられない事情があることをご説明しました。
しかしながら、合否の判断が行われた結果で面接時間が縮まる場合もあります。
以下に、採用の判断がついた場合と、不採用の判断がなされた場合それぞれについて、面接が早く終わる理由をご説明します。
採用の場合
採用が決まった段階で、面接を早めに切り上げることがあります。
冗長な面接をするのは不合理だからです。以下に、例を挙げてご説明していきます。
既に採用が決定している
最終面接で、既に採用が決定している場合には、面接時間が短くなることが多いでしょう。
なぜなら、最終的な意思確認や質疑応答、事務的な説明のみが行われるからです。
最終面接は意思確認が主な目的であるという企業も少なくありません。
また一次面接や二次面接において、事前のインターンシップでの評価やリクルーターからの推薦によって、ある程度面接通過が決まっている場合もあります。
面接通過が決まっている場合でも、見た目の不公平感が出ないよう他の就活生と同じフローを行う必要があるのです。
さらに、書類選考である程度合格が決まっている場合もあります。
面接では身だしなみやコミュニケーション能力のみを確認するということも少なくありません。
以上のように、面接をする前からあらかじめ結果が決まっている場合は、早めに面接を切り上げることがあります。
マッチングがスムーズに進んだ
マッチングがスムーズに進んだ場合、採用が決まった段階で早めに面接を切り上げることがあります。
多くの候補者を見ている企業側にとって、特に目を惹く就活生の内定は確保しておきたいからです。
また、大企業の選考においては、候補者が多いため面接時間が少なくなりがちです。
マッチングがスムーズに進んだかどうかはどのように判断できるでしょうか?
たとえば、質問に対して簡潔に応えられた場合や、面接官が詳しく聞き返さなくても良いくらいまとまった回答ができた場合が挙げられます。
聞き返しや深堀の質問を重ねる必要がなくなるため、他の候補者よりも短い面接時間で済むのです。
また、身だしなみが整っている、はきはきしている、表情が良いなどの評価点が多く積み上がった場合も考えられます。
話の内容以外に好印象を与えることで、面接時間を少なくすることができるのです。
不採用の場合
不採用の場合、面接時間を長く取ってしまっては他の候補者の対応をする時間が不用意に削られてしまいます。
そのため、落とす場合に早めに面接を切り上げることがあります。以下に、その例をご説明していきます。
マッチングが上手くいかなかった
マッチングが上手くいかなかった場合、企業側は就活生を落とす判断を下します。
たとえば、海外事業がないのに海外経験や英語力ばかりをアピールしたり、営業職の募集なのに事務的な職を希望したり、全国転勤を許容する学生を募っているのに地元に留まりたいアピールをしたりする場合が挙げられます。
企業の求める人物像でなければ、どんな立派なアピールも無駄になります。
面接に臨む前には募集要項や企業のホームページをくまなく確認し、それに合わせた自己PRや志望動機などを展開しましょう。
面接官が応募者に興味を持てなかった
面接官が応募者に興味を持てなかった場合は、落とされる可能性が高いため面接が早く終わる傾向にあります。
たとえば、個性のない定番の返答を繰り返したり、声が小さく委縮した態度であったりすることが挙げられます。
あまり会話をしたくない、または会話が続かない就活生には、面接官も決まった最低限の質問しか投げません。
個性的な回答を用意したり、会話のキャッチボールを意識してコミュニケーションを円滑に行ったりする必要があります。
しかしながら、単に面接官との相性が悪かったという不運も考えられます。
面接官も1人の人であるため、直感的に落としてしまうこともあるでしょう。
その場合は、運が悪かったと早めに気持ちを切り替えることも必要です。
面接の前から不採用の可能性が高かった
面接の前から不採用の可能性が高かった場合、面接に割く時間が無駄になるため早く終わらせます。
たとえば、事前のメールや待合室での態度が悪く失礼だった、履歴書などの書類不備や服装の乱れなどがあった、事前のインターンやリクルーター面接で評価が悪かったなどの場合が挙げられます。
いくら不採用が決まっているからと言っても、前もって面接の機会を提供すると決まっている手前、形式上だけでも面接を行う必要があるのです。
面接が早く終わる時に振り返りたいこと
面接が早く終わってしまい、不安になるシーンは少なからずあります。
そんな時に、適切に振り返れるかどうかが、就活の成否を左右します。
早く終わってしまったという結果だけを受け取るのではなく、内容についてもう一度確認し、次に生かすようにしてください。
以下に、採用の可能性が高い例と、不採用の可能性が高い例についてそれぞれ挙げていきます。
採用の可能性が高い例
以下に挙げる例を多く経験することで、採用の可能性を上げることができるでしょう。
入社について具体的な話が出た
入社について具体的な話が出た場合、採用の可能性が高くなります。
たとえば、入社後の配属希望先を聞かれたり、他に選考中の企業について深く聞かれたりすることが挙げられます。
企業側としては、入社に関連する話だけ確認をしたいという目的で面接を行う場合もあります。
深いコミュニケーションができた
深いコミュニケーションができた場合、面接は成功したと考えても良いでしょう。
なぜなら、興味を持って深堀してくれた証だからです。
たとえば、自己PRで述べたことについて前のめりで追加の質問をされた、志望動機に関する深堀の質問があったなどが挙げられます。
深堀の質問が多いのは、面接官が興味を持ってくれている証拠です。自分の深い話が出来た場合は、採用の可能性が高くなります。
個人的な意見を共有してくれた
面接官の個人的な意見を共有してくれた場合、面接が成功したと捉えられます。
なぜなら、就活生のことを本当に思って出た言葉であることが多いからです。
たとえば、「自己PRのここがよかった」「もっとこの話が聞きたかった」「これからここを伸ばしてほしい」などの発言が挙げられます。
このようなアドバイスがあった場合は、たとえマイナスなことがあったとしても、面接に合格したり採用されたりすることが多くなってきます。
不採用の可能性が高い例
不採用の可能性が高い例を把握しておくことで、次回からの面接を改善できるかもしれません。
以下のようなことがあった場合は、もう一度自己PRや志望動機を練り直してみてください。
メモを取らなかった
面接官がメモを取らなかった場合、不採用の可能性が高くなってきます。
面接官はたいていチェックシートのような書類を持っています。
就活生に興味がない場合や落とすことが決まっている場合には、この書類に記入しないこともあるでしょう。
しかしながら、既に合格が決まっている場合でも、書類の記入をしない時があります。
一概にメモを取らなかったからと言って、不採用が決まるとは言い切れません。
深いコミュニケーションがなかった
定番の質問のみで、深いコミュニケーションがなかった場合は、落ちている可能性が高いと言えます。
就活生としては、自分をアピールしきれなかったと手ごたえの薄い結果となるでしょう。そのため、振り返りもしやすいと言えます。
しかしながら、深いコミュニケーションがなくても面接に合格することがあります。
それは、あらかじめ合格が決まっていたり、面接のフローが決まっていたりするからです。
面接が早く終わる時の対処法
面接が早く終わることが多い場合や、面接が早く終わりそうだと察知した場合には、どのようにすれば挽回できるのでしょうか。
対処法は、質問がきやすい自己PRを用意すること、会話のキャッチボールを意識すること、逆質問で熱意をアピールすること、外見を改善すること、企業研究を綿密に実施することの5つです。
1つ目は、質問がきやすい自己PRを用意することです。
あえて全てを説明することを避けることで、相手に興味を持ってもらうテクニックです。
たとえば、英語の勉強を頑張ってTOEIC高得点を取ったことを話す流れで、ボランティアや留学も経験したと話すことなどが挙げられます。
そうして面接官から深堀の質問が来るでしょう。関連する話をうまく展開できれば、挽回の可能性は十分にあります。
2つ目は、会話のキャッチボールを意識することです。
たとえば、面接官の何気ない一言について返答を行うことが挙げられます。自然な会話に持って行くことができれば、コミュニケーション能力を評価されるかもしれません。
3つ目は、逆質問で熱意をアピールすることです。
就活では面接の最後に、「何か質問はありませんか」という文言があることが大多数です。
面接が早く終わりそうな時は、最後のチャンスになるでしょう。
ぜひ熱意の高さをアピールするようにしてください。
たとえば、「御社の最新ニュースを拝見して自分の能力を活かせると感じました。新入社員からでも新しいプロジェクトに携わらせてもらえるのでしょうか?
また、どうのようにすれば良いでしょうか?」などの質問が挙げられます。
4つ目は、外見を改善することです。就活における面接は、第一印象が重要です。特に面接時間が短く設定されている大企業の場合は、見た目で判断されることもあるので注意ましょう。
たとえば、身だしなみを整える、自然な笑顔を作る、はきはきと話す、姿勢を良くするなどが挙げられます。
5つ目は、企業研究を綿密に実施することです。
企業が求めている人材でなければ、すぐに面接で落とされてしまうからです。
自己PRや志望動機は、受ける企業ごとに見直す必要があります。
たとえば、国内事業のみに注力している企業であれば海外経験に関するアピールを控えることなどが挙げられます。
面接が早く終わって不採用になった場合は、振り返りを行うチャンスです。
上記のような対策を取ることで、改善が促され、以降の就活を有利に進めることができるきっかけになるかもしれません。
面接が早く終わっても不採用が確定したわけではない
就活において、面接にかかった時間は面接の合否を確認するうえであまり重要な情報ではありません。
むしろ、面接の内容の方が大切です。
面接が終わったら、その都度しっかりと振り返る必要があります。
一般的には、話が尽きるため面接が早く終わって不採用にされたということが多いでしょう。
しかしながら、圧倒的に高い評価をされた結果で早く面接が終わる場合もあります。
自分がどちらの立場にいるのか確認できるようにしましょう。
この記事を参考に、就活を有利に進めていってくれれば幸いです。